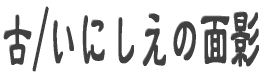 其の五十六
其の五十六怪しい親父輪っぱの会 別館 一人歩き編です。
| 更新日 2004年06月11日 金曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
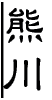 |
約2,000年前崇神天皇の御代、大和朝廷統一にあたって、
大彦命が向かわされ、その孫、六雁命が若狭国造を賜りました。 若狭の国は奈良時代以降、都との交流が繁しく、 めざましい文化の発展をしました。 江戸時代に至りてからは小浜藩の沿下となり、 京畿の要路として発展し、明治4年廃藩置県、 同14年2月福井県に、同22年市町村制施行によって、 鳥羽、瓜生、熊川、三宅、野木村として出発してきました。 古代、若狭は、朝廷に食料を献上する御食国(みけつくに)の ひとつでした。 日本海で獲れた魚や貝が遠路はるばる京都へ運ばれ、 いつの頃からか若狭人のあいだでは「京は遠ても十八里」などと 豪気なことが言われて来ました。 18世紀後半から大量の鯖が若狭から京へと運ばれました。 若狭街道が、鯖の道・鯖街道と呼ばれた由来です。 (上中町HPより一部抜粋)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright c 2003 Office Young Moon. All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||